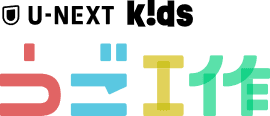「あえて外す」から生まれる、忘れられないメロディ。『うご工作』の音楽ができるまで


イトケン
音楽家
自身のバンド「イトケン with MEGAPHONES」のほか、「大友良英スペシャルビッグバンド」「蓮沼執太フィル」など数多くのバンドに参加。NHK Eテレ『ピタゴラスイッチ』『いないいないばあっ!』の楽曲制作やドラム演奏でも知られる。独創的なサウンドで子ども向け番組から実験音楽シーンまで、幅広く活躍する音楽家。
物の“うごき”の面白さに着目した、U-NEXTオリジナルの工作番組『うご工作』。スマホやタブレットと視聴者が“協力”し、面白いものを作る成功体験を通して、“何かを作ること”の楽しさを子どもたちに届ける番組です。
本作の音楽を担当したのが、NHK Eテレ『ピタゴラスイッチ』の録音や『いないいないばあっ!』の音楽制作でも知られる、音楽家のイトケンさんです。これまで数多くの映像を共に手掛けてきた映像作家・デザイナーの石川将也さんとタッグを組んだ本作。一度聴いたら忘れられない、遊び心に満ちた音楽の数々は、いかにして生まれるのでしょうか。「セオリーからあえて外す」独自の哲学から、『うご工作』でも取り入れたという「違和感のある音」へのこだわりまで、『うご工作』を含むイトケンさんの音楽制作の背景を紐解きます。
「音楽活動にすべてを懸けよう」と思えたきっかけ
──まずはイトケンさんのこれまでの活動について、簡単にお聞かせいただけますか?どのような経緯で、音楽の道に進まれたのでしょうか。
イトケン : 私は元々ミュージシャンではなかったんです。大学の工学部を卒業して、ミキサーなどを作る楽器メーカーに就職し、開発の仕事をしていました。1992年に入社したのですが、98年には辞めることになります。
というのも、他の制作の仕事をしている知り合いも増えて、色々なオファーをいただけるようになって。一方で、会社に入ってから組んだバンド活動では、海外ツアーにも行くようになっていました。
その頃は、ちょうど世の中が“デジタル”への転換期。会社で仕事を続けるには、しっかり勉強し直さなければならないタイミングでもあって。「その時間を費やすなら、音楽活動にすべてを懸けてみてもいいのかな」と思い、退職を決めました。
──会社員時代は、音楽活動で生きていこうというよりは、趣味という感覚だったのでしょうか?
イトケン : 趣味ですね。当時はまだメジャーとインディーズがはっきりと分かれていた時代で、私たちがやっていたのは非常にマイナーな音楽でしたから。それで食べていくという考え自体がありませんでした。
それが95年頃になると、ミュージシャンの小山田圭吾くんが『トラットリア』というレーベルを始めたのをきっかけに、メジャーとインディーズの垣根が少し曖昧になってきた。「もしかしたら音楽で食べていけるのかもしれない」と思い始めたのは、その頃でしたね。
──そこから『ピタゴラスイッチ』などのお仕事に関わっていくわけですね。本作の監督を務めている石川将也さんとの最初の出会いもその頃ですか?
イトケン : そうですね。会社を辞めてゲーム音楽などの仕事をいただいている中で、栗コーダーカルテットの栗原正己さんが参加している『DCPRG』というバンドに、トラ(※)で入ってくれないかと誘われたんです。それで「録音があるから参加してくれない?」と誘われたのが、当時、新番組だった『ピタゴラスイッチ 』だったという流れですね。それがきっかけで、本格的に子ども向け番組の世界に入っていきました。
※エキストラの略。バンドなどで一時的に欠員が出た際に、代理で演奏するミュージシャンのこと
メロディが印象的な主題歌は「歌詞ではなく、曲から先に生まれた」
──『うご工作』の音楽制作においては、具体的にどのような部分を担当されているのでしょうか?
イトケン : 各コーナーのBGMがメインです。また、コーナーによってはテーマ曲もあるので、石川くんが手がけているコーナーの音楽は、基本的にすべて担当しています。曲は自宅で自分一人で完成させる場合もありますし、バンドサウンドにしたいという要望があれば、メンバーをスタジオに呼んで演奏してもらい、その音源から自分が完成させるという形もあります。

『うご工作』監督の石川さんは2020年の独立以降、イッセイミヤケを始めとするクライアントワークや、自身発のプロジェクトなど、数多くイトケンさんに音楽制作を依頼してきたそう
──今回『うご工作』に関わることになったのは、どんなきっかけからだったのでしょうか?
イトケン : 石川くんがcogという会社を立ち上げてから、彼が個人で請け負う仕事の音楽を色々と担当させてもらっていたんです。その流れで、「U-NEXTでこういうコンテンツがあるんだけど、やってくれませんか」とオファーを受けました。
──最初に番組のテーマを聞いた時の印象はいかがでしたか?
イトケン : 「いつもの石川くんのテイストだろうな」というのはすぐにわかりました。ですから、すんなりと理解できましたし、どんな音楽にするかのイメージもしやすかったです。
──制作を進めていく中で、そのイメージに変化はありましたか?
イトケン : ほとんど最初のイメージどおりでした。ただ、コーナーによっては「あ、これはいつもと違うんだ」という発見もありましたね。
石川くんの作る映像って、クールで淡々としている印象なんです。なので、音楽で抑揚をつけすぎるようなことはあえてしないように、いつも意識しています。今回も、そのイメージで曲を作っていきました。
でも『うご工作エンジン1号』の曲については、石川くんから「これはもうちょっと楽しくしたい」と。何度かテイクを重ねましたが、これまで一緒につくった作品も踏まえると、少し意外なリクエストではありましたね。
──石川さんとは、どのようなやり取りで制作を進めるのですか?
イトケン : お互いにどういうものを出してくるかは、もうなんとなくわかっているんです。石川くんから映像が送られてきたら、私がそれを見てすぐに作業を始めて、何往復かやり取りをしていく。そのうちに、数時間後には完成しているという感じが多いですね。
私はたぶん、「これだな」と思ってパッと作ったり、相手に打ち返したりするのが早い方だと思います。仕事相手ごとに、自分の中に"引き出し"があって「今回はこれかな」と引き出しから選んで投げてみると、すんなりいけることも少なくない。もちろん、「これはちょっと時間をかけて考えないと無理だな」という場合もありますけどね。
──今回の制作で、特に印象に残っていることはありますか?
イトケン : オープニングになっている主題歌ですね。石川くんが「歌詞がなかなかできない」と言っていて。それで「先に曲を作りましょうか」と私から提案して、2パターンの曲を出したんです。そうしたら「それぞれのサビをAメロとBメロにしてみたい」と言うので、合体させてできたのがあの主題歌です。
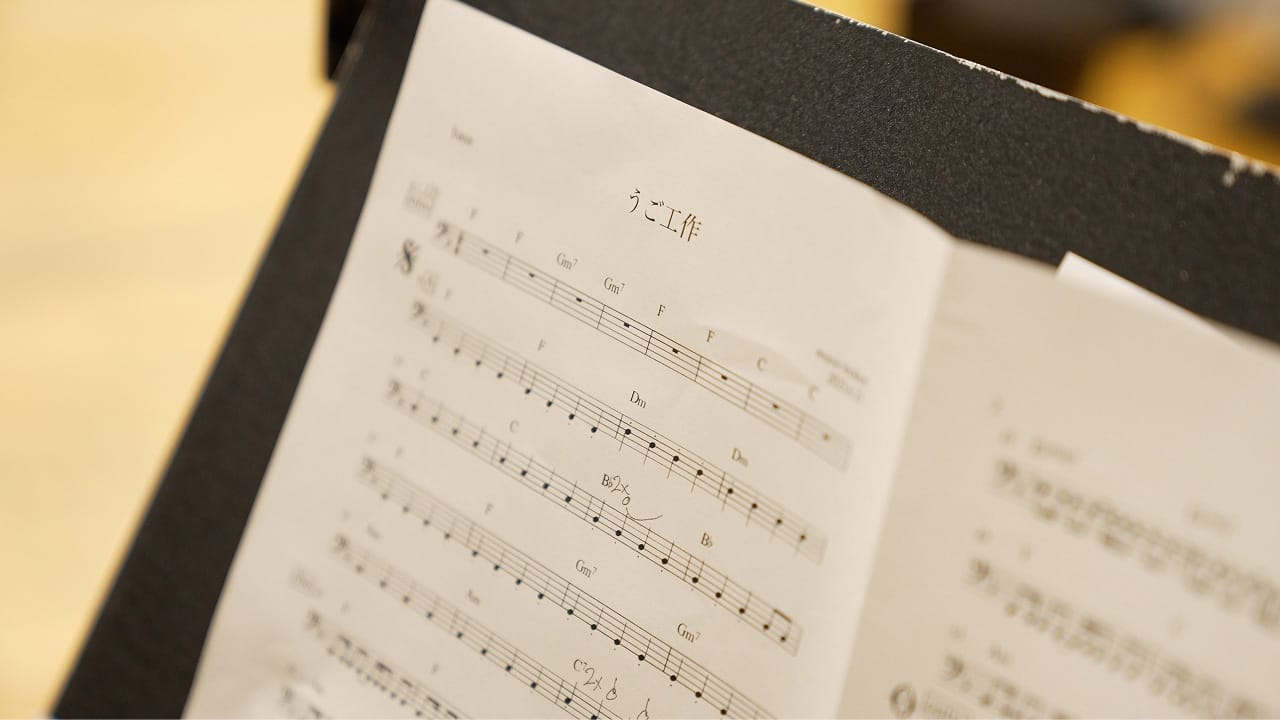
──主題歌は曲が先にあったんですね。歌詞がまだない段階で、何を手がかりに作曲されたのですか?
イトケン : 石川くんの中に、「こういう曲にしたい」という具体的なイメージはあったんです。その雰囲気に寄せられるように作って投げてみた、という感じですね。
──主題歌は一度聴くと忘れられない、耳に残るメロディが印象的です。制作において、特に意識したことはありますか?
イトケン : 特にメロディの部分で、「難しくならないように」というのは意識しました。結果として、インスト版の曲に子どもたちが作った工作の動画を乗せるだけで、色々な世界が生まれるような仕上がりになっていると思います。この曲が、どんどん広がっていってくれると嬉しいですね。

主題歌収録時のひと時。夢眠ねむさんも一緒にリラックスしたムードで収録が進む
「少し違和感のある音が、かえって良かったりする」
──イトケンさんは子ども向けだけでなく、様々なジャンルの音楽を手がけられています。どんなジャンルをやる上でも、共通して大事にしていることはありますか?
イトケン : 「自分にしか出せない音色」を必ず入れるようにしています。日常的に色々な音を自分で作ったり、サンプリングしたりしているのですが、それらを使うことで「自分だけの音色」になります。
使うとそれっぽくなる、よく使われている音源というのは世の中にたくさんあって。つい取り入れたくなるものですし、もちろん、私もそういった音源を使うことはありますが、そのうえで、そこに「よくわからない違和感のある、自分だけの音」を入れると、急に違う仕上がりになるんです。
──『うご工作』においては、どんな独自の音を取り入れましたか?
イトケン : U-NEXTのロゴが出てくるアバンタイトル(番組冒頭の短い映像)には、自分が生で録った車のサスペンションの音を入れています。映像の動きを見た時に「この動きはサスペンションだな」と直感したんです。そこで自分で中古のサスペンションを買って、それを鳴らした音を入れました。サスペンションの部品であるスプリングって、すごく良い音がするんですよ。
ほかには、石川くんの映像のクールさをより演出するために、エレピ(エレクトリックピアノ)の音をよく使っています。それも、パチパチっとノイズが入っていたりする、「ちょっとダメなエレピの音」なんです。
綺麗な音よりも、少し違和感のある音の方が、かえって良かったりするんです。普通ならノイズをカットしたり下げたりするところを、あえて残したり、音量を上げて目立たせたりすることも少なくありません。
──イトケンさんにとっての「自分らしい音」をあえて言葉にすると、どんな表現になりますか?
イトケン : 「きっちり合っていない音」でしょうか。チューニングがズレていたり、打楽器のタイミングがバラバラだったりする音のほうが、私は好きなんです。「ジャン!」と一斉に鳴るより、「ジャララン」みたいに少しずれる方が、演奏している人数感も出て、ちょっと面白くなるんですよね。
──教科書的には正解ではない音を取り入れながら、ひとつの音楽として成立させる。そのためのさじ加減に、イトケンさんらしさを感じます。
イトケン : どこまでやっていいか、音楽的に成立するギリギリのラインは、多分ひとつしかないと思うんです。あとは映像との兼ね合いもありますし、経験則によるところが大きいでしょうね。

「私たちが思いもつかない、楽しみ方をしてほしい」
──子ども向けジャンルの音楽を作るとき、特に意識していることはありますか?
イトケン : たとえば「ここはラッパの『プワ〜』って音を入れた方がいいな」といったように、映像の動きに効果音をしっかり当てていくことを重視しています。
でも、今回の『うご工作』はいつもの作り方とちょっと違います。楽器はピアニカやトイピアノなど、いわゆる"子どもっぽいもの"を使っていますが、表現としてはそこまでデフォルメしないように意識したんです。
──イトケンさんの中には、「子ども向けを作るときのモード」のようなものがあるのでしょうか?
イトケン : それはあるかもしれないです。でも、すごく意識してそのモードに切り替えている感覚はないです。楽器を立ち上げて、映像を見ながら「このくらいのテンポで、こういう感じかな」と弾き始めると、気づいたら自然とそのモードになっていく。作っている最中は、「子どもだからこの音を使おう」とかも特別考えてはいません。「完成したら勝手にその音になっていた」という感覚のほうが近いですね。
──『うご工作』という番組が、視聴者にどんなふうに届いてほしいと思いますか?
イトケン : 番組を見ながら、親子で一緒に作ってみてもらいたいですよね。パッと見てすぐできるような工作がテーマのコンテンツですから。
U-NEXTという媒体で、視聴者の皆さんがどんなふうに受け取ってくれるのか、まだうまく想像できていない部分もあります。スマホで見ながら同時に作業してくれるのかどうかも含めて、この作品がどう広がっていくのか、とても興味深く思っています。
──配信番組ならではの、新しい視聴体験への期待ですね。
イトケン : そうです。今後の番組作りにも、関わってきますよね。私たちが思いもつかないような楽しみ方をしてくれる人がいるかもしれない。そういう反応がうまく私たちのもとにもフィードバックされたら、さらに面白くなっていくだろうなと想像しています。